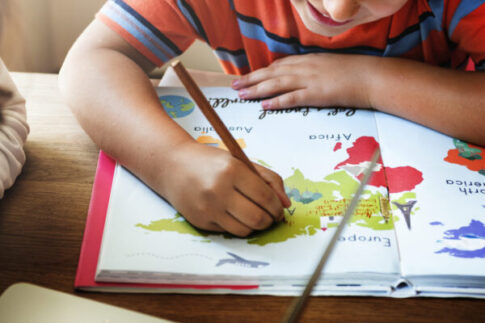1871年創立の長い歴史を持ち、男子校の最難関中学校の一つでもあります。
今回は開成中学校の受験予定者なら知っておきたい、学校の特色や受験情報、入試問題の傾向などをご紹介していきます。
目次
開成中学校の特色
開成中学校・高等学校では「開物成務」「ペンは剣よりも強し」「質実剛健」「自由」の4つを教育理念とし、「たくましい大人として生きるために」という教育方針のもと、中高一貫で幅広い教育が行われています。
「共に立て、共に育てていく」という「共立」の精神を軸に、「(開物)素質を開花させ、(成務)人としての務めを果たす」を由来とし、開成中学校という校名になりました。
中高での授業は6日制の週34時間となり、高校からは特に理科や地歴・公民、芸術科目が細かく設定されています。また、高校での募集も行われ、高校2年からは内部進学者と高校からの入学者の混成クラスとなります。
さらに高校では、実力考査や模擬試験が年に数回実施されます。中学では基礎学力が重視される一方、高校では受験に力を入れたきめ細かな教育課程が特徴的です。
学校の沿革
開成中学校・高等学校の歴史は、1871年に「共立学校」が創立されたことが始まりとなります。1895年には校名を「開成」とし、1948年には開成高等学校が発足しました。
1960年には高校からの公募も開始され、現在に至ります。
進学先・合格実績
2023年度の大学入試結果を見ると、東京大学148名、早稲田大学192名、慶應義塾大学163名など、難関大学への合格実績が豊富です。
このうち進学者数を見ると、東京大学146名、早稲田大学37名、慶應義塾大学38名となり、東京大学への進学者数が圧倒的に多いことが特徴です。
施設
主な施設は、中学校舎、高校普通教室棟、高校特別授業棟のほか、理科実験室、小講堂、天体観測ドーム、視聴覚教室、コンピューター室、図書室、食堂、第1グラウンド、第2グラウンドなどがあり、充実した施設環境が整っています。
学校周辺の環境
開成中学校の最寄り駅は西日暮里駅となります。
西日暮里駅はJR線、東京メトロ千代田線、日暮里・舎人ライナーが乗り入れ、さまざまな方面からのアクセスに優れています。
開成中学校の受験情報
試験日
2024年2月1日(木)
募集人員
男子300名
試験科目と試験時間・配点
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 国語 | 50分 | 85点 |
| 算数 | 60分 | 85点 |
| 理科 | 40分 | 70点 |
| 社会 | 40分 | 70点 |
偏差値
開成中学校の偏差値(80偏差値)は71となり、男子校の最難関中学校の一つとなります。
倍率
2023年度の入試結果より、受験者数は1193名、合格者数は419名、倍率は2.8倍となっています。
入学後の学費
2024年度の学費は以下の通りです。
| 入学金 | 320,000円 |
| 施設拡充資金 | 120,000円 |
| 授業料(月額) | 41,000円 |
| 施設維持費(月額) | 6,000円 |
| 実験実習科(月額) | 6,000円 |
| 父母と先生の会会費(月額) | 2,800円 |
| 生徒会会費(月額) | 550円 |
上記の費用以外に、学級費(教材費など)が115,000円発生します。
開成中学校の入試問題と対策
算数
試験時間は60分、配点は85点満点となります。大問は4問で、図形、速さ、場合の数、数の性質、規則性などをはじめ、まんべんなく出題されています。
問題数はそこまで多くありませんが、いずれも難易度が高く、時間的な余裕は少なくなります。思考力が求められる問題、複雑な計算・作業を要する問題などが多く、スピードと正確さの両立が試される試験です。
頻出分野はもちろん、どの分野が出題されても対応できるよう、それぞれ標準・応用レベルまでしっかり学習し、実力を磨かなくてはなりません。
また、その場で思考する力、臨機応変に計算・作業を進める力も必要ですので、問題演習を通じて実戦的な力を鍛える必要があります。
過去問はもちろん、似た傾向の問題に数多く触れ、どのような問題が出題されても落ち着いて速く正確に解けるよう、トレーニングを重ねましょう。
また、全ての問題で途中式や考え方を記述させる形式となっており、注意が必要です。
日頃から式や図、計算などをまとめる習慣をつけ、採点者にしっかり伝わる記述力を鍛えましょう。
ただ解答するだけでなく、解答へのプロセスをきちんと示せるよう、普段から練習を重ねることが重要です。
国語
試験時間は50分、配点は85点満点で、算数より若干短めの試験時間となっています。
大問は2問で、説明文、小説文、随筆文、詩などの読解問題が2題出題されます。
設問形式は記述問題が多く、難易度の高い設問が目立ちます。また、文章も複雑な内容が目立ち、読解に時間がかかります。
大問数としては少ないですが、文章のレベルと設問の難易度を考えると、時間的な余裕があるとは言えません。
本文を読む前にあらかじめ設問の内容を頭に入れておき、きちんと設問を念頭に置いて読む必要があります。
素早く内容を把握する速読力、各設問をテキパキこなす情報処理能力など、実戦的な力が求められる試験です。
また、読解問題は単に説明文と小説文が出題されるわけではなく、随筆文が出題される場合のほか、詩の出題も見られます。
出題傾向がバラバラなので、どの分野が出題されても対応できるよう、日頃から問題演習を通じて慣れを作る必要があります。
さらに、読解問題の小問に漢字などの知識問題も含まれます。こちらもしっかり対策し、語彙力を高めておきましょう。
また、語彙力は知識問題だけでなく、本文や設問を正確に把握する際にも必須です。過去問演習はもちろん、普段から問題演習を通じて語彙を意識し、実力を伸ばしていきましょう。
社会
試験時間は40分、配点は70点満点です。大問は3~4問で、地理・歴史・公民分野(時事問題含む)から幅広く出題されます。
設問形式は選択肢問題、適語記入問題、記述問題などがあり、いずれも基本問題が中心となっています。受験生のレベルを踏まえると高得点勝負になりやすく、一問のミスが大きな差につながるおそれがあります。
基本問題が中心だからといって油断せず、日頃から幅広い分野の基本知識を繰り返し確認し、知識の精度を高めておきましょう。ケアレスミスは絶対に避け、着実に得点を積み重ねる必要があります。
また、各分野が混ざって出題される総合問題も見られるので、しっかり対策しなくてはなりません。
設問ごとに各分野の知識をきちんと引き出せるよう、総合問題の形式に慣れを作っておく必要があります。過去問演習をはじめ、問題演習でも総合問題に触れ、トレーニングを重ねましょう。
さらに、試験時間も短いため、資料などの情報は素早く読み取らなければなりません。
こうした実戦的な力も必要ですので、単なる暗記で終わらせず、過去問演習・問題演習ともに徹底し、傾向に沿った実力を養うことが大切です。
理科
社会と同じく、試験時間は40分、配点は70点満点となります。大問は4問で、4分野からまんべんなく出題されています。
設問形式は選択肢問題、適語記入問題、計算問題のほか、記述問題、作図問題なども見られます。
社会同様、基本問題を中心に出題されますが、実験・観察問題をはじめ、思考力が求められる問題もあり、注意が必要です。
こちらも高得点勝負になる可能性があるので、基本問題でのケアレスミスは絶対に避け、しっかり得点源にしましょう。
そのうえで、思考力が必要な問題にもテキパキ対応し、周りの受験生と差をつけることが重要です。過去問演習はもちろん、似た傾向の問題演習も積み重ね、日頃から思考・考察する習慣をつけましょう。
また、試験時間にもそこまで余裕はないので、過去問演習から時間配分の感覚をつかみ、常に時間を意識して解き進めるようにしましょう。
特に思考力が必要な問題で時間をかけすぎると、ほかの基本問題に手が回らなくなるおそれがあります。
一歩時間配分を間違えると大変ですので、スピーディーかつ正確に解き進めるよう、日頃から意識して対策を行いましょう。
資料などの与えられた情報も素早く読み取り、各設問をテキパキこなす、実戦的な力を磨く必要があります。
過去問
受験生平均点の特徴
受験生平均点
| 平均点(310点満点) | 平均点割合 | |
| 受験生 | 221.5点 | 71.4% |
| 合格者 | 251.5点 | 81.1% |
科目別平均点
| 国語(85点満点) | 算数(85点満点) | 理科(70点満点) | 社会(70点満点) | |
| 受験生平均点 | 49.0点 | 61.7点 | 56.9点 | 53.9点 |
| 合格者平均点 | 55.6点 | 76.4点 | 61.5点 | 57.9点 |
科目別に受験生平均点と合格者平均点の結果を見ると、特に算数で差がつきやすい傾向があります。
また、例年の傾向を見ても、算数では合格者平均点が受験生平均点を大きく上回ることが特徴です。
開成中学校合格のために必要なこと
開成中学校は、試験日が1日しかありません。そのため、1日の中で全力が出せるような練習をしておく必要があります。
男子校の中でも最難関中学校の一つとなり、特に算数と国語はかなり難易度が高いです。
また、社会と理科は基本問題が中心となりますが、その分高得点勝負になりやすく、ケアレスミスは絶対に避けなくてはなりません。
こうした点に注意し、科目ごとの特徴に沿った対策を進める必要があります。
例えば算数であれば、どの分野が出題されても対応できるような実力を磨くこと、そして途中式や考え方などをきちんと示す練習をすること、国語は語彙力、速読力、記述力など、特に実戦的な力を意識すること、社会と理科は基本問題をしっかり得点源としつつ、難易度の高い問題にも対応して差をつけること、など、それぞれの傾向に合わせた対策を進めましょう。
もちろん、どのような傾向が出題されても焦らず、テキパキ対応していけるような、盤石な実力も必要です。
傾向に沿った対策は大前提ですが、基本知識の精度をとにかく高めておくこと、日頃から思考する習慣をつけること、情報処理能力を磨いておくことなど、一歩進んだ対策を行い、本番に臨むようにしましょう。